Story about“Uji Matcha”
N°1宇治地区の茶畑風景

宇治地域の茶畑は、山間地ならではの急斜面に広がり、そこでお茶が育てられています。
さらに、昼夜の気温差が大きく朝霧が発生しやすい気候が、宇治茶の「香り」を育む要因といわれています。
N°2「旨み」と「甘み」が豊かになる理由
宇治抹茶を生み出す栽培方法

抹茶の特徴のひとつは、ほろ苦さです。また、一般的に飲まれる煎茶と比べると、豊かな旨みと甘みが感じられます。これらの違いは、特別な栽培方法によるものです。
抹茶の秘密は「覆下(おおいした)栽培」と呼ばれる、茶畑を黒い布で覆う独自の方法に隠されています。
この「覆下栽培」という技術は宇治で生まれ、茶摘みの20日以上前から茶畑を覆う作業が行われます。

「覆下栽培」は、安土桃山時代に宇治で始まった伝統的な栽培方法です。4月に新芽が出た時期に、ヨシズや黒布などで茶畑を覆い、日光を遮る(遮光率98%)ことで茶畑の光合成を抑制します。
光合成の抑制により、茶葉中の旨み成分であるアミノ酸が、渋み成分であるカテキン類に変わるのを防ぎ、渋みが少なく旨みの濃いお茶が育まれます。
この技術は霜から茶葉を守るために考案されたものでしたが、茶の風味を高める事がわかり、広く普及しました。
N°3宇治抹茶
その歴史と成り立ち

千利休による「茶の湯」が大流行していた室町時代。
この宇治独特の製法で作られた茶葉から生まれる抹茶は、 独特の気品溢れるまろやかな味で時の将軍らを魅了したと言われています。
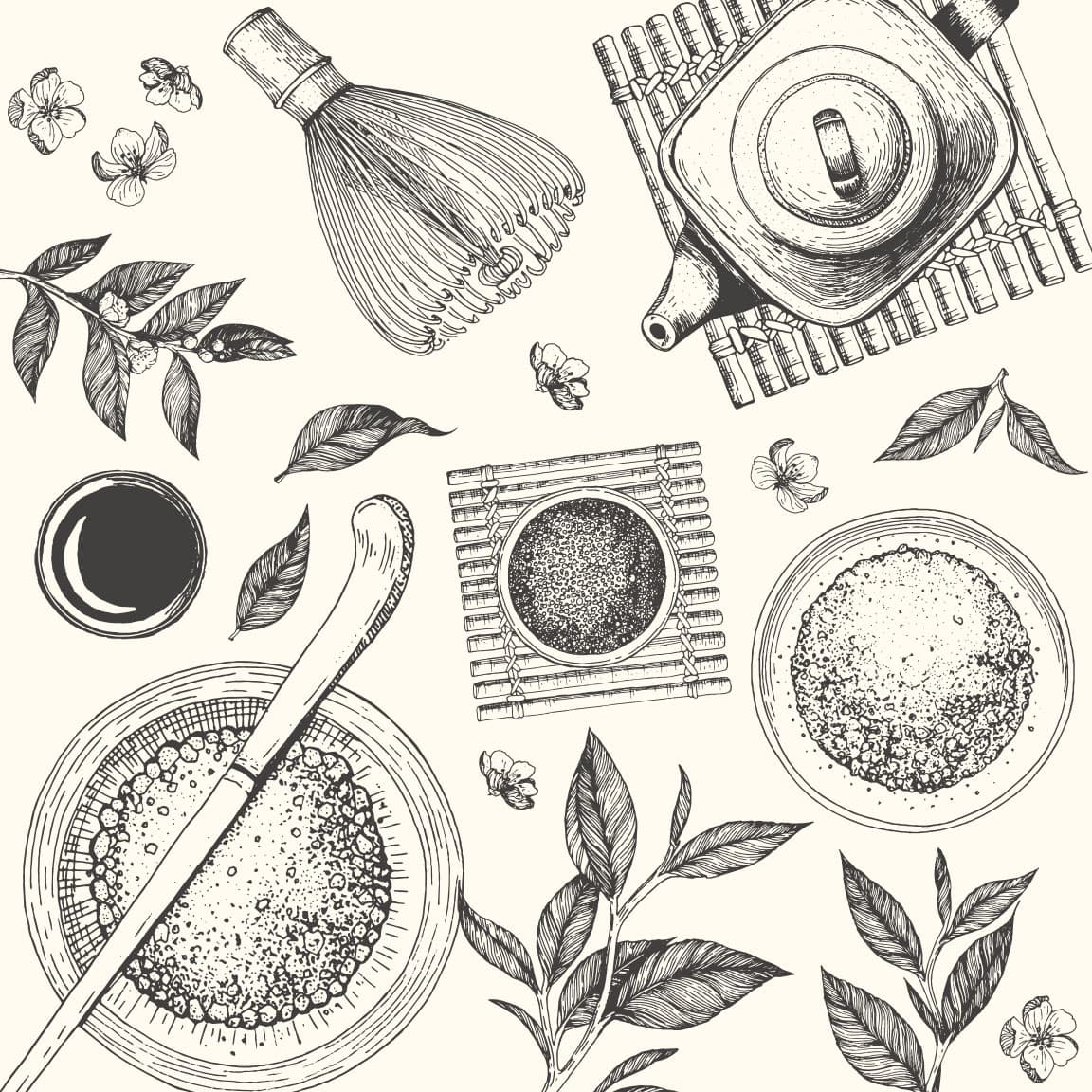
一般的に、お茶の産地としては静岡、鹿児島、埼玉(狭山)などが代表的に知られています。
しかし、抹茶といえば「宇治抹茶」を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
その理由として、大きく3つのポイントが挙げられます。
-
1.緑茶発祥の地としての歴史
華厳宗の僧・明恵上人が、京都栂尾の高山寺に茶を植えたことが、日本最古の茶園とされています。
-
2.茶栽培に適した環境
気候風土:山間部特有の昼夜の寒暖差が大きく、良質な茶葉の栽培に適しています。
技術:現在日本各地に普及している多くの栽培技術や製茶法の多くは、宇治で確立されたものです。 -
3.豊かな風味と奥深い味わい
茶栽培に適した気候と技術によって、宇治抹茶は香り高く、程よい苦味と豊かな旨味が調和した「奥深い味わい」が特徴となっています。
これらの理由により、単なるブランド力だけでなく、歴史的背景や自然環境、優れた技術に支えられた宇治抹茶は、今なお高い評価を受け続けています。







